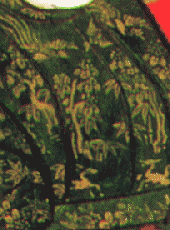|
猿丸大夫 (生没年不詳・元慶年間(877〜884)の人物か?) |
| 謎の人物 | |
| 風折烏帽子に萌黄色唐草丸文様の狩衣、浅黄色の指貫。 謎の人物、猿丸太夫であるだけに、どう描くか苦労したようです。指貫の色で地下人を表しているのかもしれません。平安初期には時代的に合いませんが、それは仕方がないでしょう。 |
|
| 奥山に 紅葉ふみわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ 秋はかなしき 「古今集」 | |
 |
中納言家持 =大伴家持 (718〜785) |
| 従三位中納言兼春宮大夫 | |
| 垂纓冠に黒袍、浮線綾文様の下襲の裾を長く引く典型的な文官束帯。 奈良時代の人物である家持にはまったくそぐわない装束です。 袖口から覗く紅の単が美しい色合いです。 |
|
| かささぎの わたせる橋に 置く霜の 白きを見れば 夜ぞ更けにける 「新古今集」 | |
 |
陽成院 (868〜949) |
| 第57代天皇 | |
| 御引直衣を模した装束のようです。 繁紋の垂纓冠に桐と竹の文様のある直衣、紅色の長袴という装束は天皇の地位をよく表していますが、直衣は短く「引直衣」には見えません。また江戸時代の冬の御引直衣は桐竹紋ではなく小葵文様でした。檜扇も蘇芳色に染めたものを持たせれば、さらに故実に則ったものとなったでしょう。 |
|
| 筑波嶺の 峰より落つる みなの川 恋ぞつもりて 淵となりぬる 「後撰集」 | |
 |
河原左大臣 =源融 (822〜895) 嵯峨天皇の皇子 |
| 従一位左大臣 | |
| 繁紋の垂纓冠に薄紫色、轡唐草文様の袍を束帯で着ています。この薄紫色は他の例を見ると赤袍のことのようですが、それでは従一位の身分と合致しません。ここはデザイン性を優先したのでしょう。 この画像ではよくわかりませんが、太刀は見事な飾太刀で、鍔は正式の「唐鍔」に描かれています。 |
|
| 陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし 我ならなくに 「古今集」 | |
 |
中納言行平 =在原行平 (818〜893) |
| 業平の兄 民部卿などを歴任し正三位中納言 | |
| 烏帽子直衣姿です。 立烏帽子、白で浮線綾文様の袍に紫の鳥襷文様の指貫です。手には檜扇を握っています。 身頃と奥袖は裏の縹色が透けていますが、襟と両袖、裾の「襴」が表地を引き返しているために裏地が透けずに白く見えます。これは「四白の直衣」とも呼ばれるものです。ゆったりとしたフォルムで「なえ装束」を表しているのでしょうか。 |
|
| 立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む 「古今集」 | |
 |
在原業平朝臣 (825〜880) |
| 右馬頭等をへて従四位下右近衛中将 | |
| ご存じ、色男業平は武官でした。そこで老懸をつけた巻纓冠、帯剣して矢を負い、弓を手にしている武官束帯姿です。袴は「かに霰」文様の表袴ですが、袍は夏の直衣に用いられる三重襷文様の縹色で、こうした取り合わせは通常は考えられないものです。また裏のない夏袍であるのに「四白」になっているのも奇異です。 この図は有名で、業平と言えばこのパターンとされ、そこから三重襷文様とそのバリエーションの一種が「業平菱」と呼ばれるようにもなりました。 |
|
| ちはやぶる 神代も聞かず 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは 「古今集」 | |
 |
貞信公 = 藤原忠平 (880〜949) |
| 摂政・関白 | |
| 帯剣した束帯として典型的なものです。黒袍の文様は雲立涌で、関白の地位に合致していますし、襴の部分の文様を横向きに描き分けるなど、かなり精細に書き込まれた作品です。。束帯の図としては特に問題となるところはありません。ただし、履き物として「浅沓」をはいていますが、これは「靴の沓」を用いるべきだったかも・・・。 | |
| 小倉山 峰のもみじ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ 「拾遺集」 | |
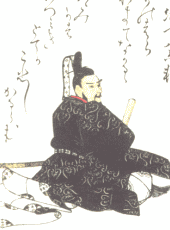 |
中納言兼輔 =藤原兼輔 (877〜933) |
| 中納言兼右衛門督 | |
| 同じく文官束帯です。石帯は巡方帯で、これは重要儀式に用いられるものです。黒袍の文様は轡唐草、やはり摂関とは差を付けているのでしょう。中納言にしては裾が長すぎるかもしれません。 それにしても平安の公卿に頬髭は似合いませんね。 |
|
| みかの原 わきて流るる いづみ川 いつ見きとてか 恋しかるらむ 「新古今集」 | |
 |
源宗干朝臣 ( ?〜939) 光孝天皇の孫 |
| 信濃・伊勢等の権守、右京太夫(四位) | |
| 冬の冠直衣です。 「四白の直衣」ですが、若く描かれていますので透ける裏地を縹色ではなく、薄紅色に描いた方が良かったかもしれません。また襟が白くなっていないために「三白」になってしまったのは絵師よりも刷師のミス?指貫は紫の鳥襷文様で、細かく描かれているため鳥がはっきりと読みとれます。 直衣で笏を持つことは通常ありません。ここは檜扇にすべきだったでしょう。 ただ、四位で冠直衣と言うことは通常ではあり得ないような破格の待遇ですね。 |
|
| 山里は 冬ぞ寂しさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば 「古今集」 | |
 |
凡河内躬恒 生没年不詳(延喜年間に活躍) |
| 淡路掾等の下級国司を歴任 | |
| 薄萌黄色無地の水干で、単は黄色、指貫は浅黄色です。手には蝙蝠扇を持ちます。 彼の身分から考えると至極妥当な装束です。絵師の有職故実への理解をしっかり見て取れます。水干の襟紐は前で蝶結びにする結び方を選んでおり、菊綴じの形状など、しっかりと描かれています。 |
|
| 心あてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花 「古今集」 | |
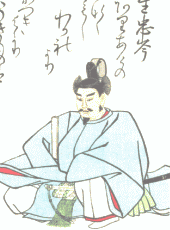 |
壬生忠岑 生没年不詳 |
| 右衛門府生から摂津権大目 | |
| 無紋縹色の袍、地下の武官の束帯姿です。 これも同じく秀逸な図です。半臂の襞もきちんと描かれ、表袴も無紋、地位に応じている図です。高位の者の太刀は金具が金ですが、彼のものは銀色で描かれ、こまかく立場の相違を描ききっています。 ただ、残難なのは遠紋とはいえ巻纓であることで、地下の武官らしく細纓にしていればさらに良かったのですが・・・。しかしまぁ、遠紋として他と描き分けていることは大したものです。 |
|
| 有明の つれなく見えし 別れより 暁ばかり 憂きものはなし 「古今集」 | |
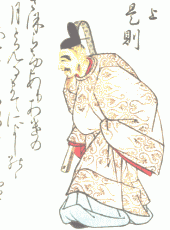 |
坂上是則 生没年不詳 |
| 大和権掾・中監物・大内記をへて従五位下加賀介 | |
| 垂纓冠の衣冠姿です。手に檜扇を持ち笏を持たないことも正しい姿です。 薄紫色の袍、これは赤袍のことのようで五位に合致しています。文様は轡唐草。このシリーズでは輪無唐草は登場せず、通用文様は轡唐草オンリーとなっています。 指貫は浅黄色無紋ですが、五位の指貫は紫無紋であり、ここは画竜点睛を欠いたというべきでしょうか。 |
|
| 朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪 「古今集」 | |
 |
清原元輔 (908〜990) |
| 河内権少掾から大蔵少丞・民部大丞等を経て五位上肥後守 | |
| 香色、唐草丸紋の狩衣、単は浅縹色、指貫は薄萌黄色です。 受領階級の日常着ということを考えると妥当な姿でしょう。衣冠や直衣ではなくカジュアルな狩衣の指貫なので、こうした色のものを用いたということを表しています。 烏帽子は風折ですが、このシリーズではよほど高位でない限り、狩衣には風折烏帽子ということにしているようです。平安末期や鎌倉時代に描かれた絵巻物では、この身分では立烏帽子を用いています。 |
|
| 契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは 「後拾遺集」 | |
 |
権中納言敦忠 =藤原敦忠 (906〜943) 琵琶の名手 |
| 左兵衛佐・蔵人頭・左近中将をへて従三位権中納言 | |
| 五位の文官束帯姿です。 赤袍、表袴は無紋ですから三位中納言には相応しくありません。それ以外についてはかなり精細に描かれています。しかし束帯の図というと決まって帯剣して前に平緒を垂らしていますが、実際に五位の文官においては、中務省の官人でなければあり得なかったことでしょう。このシリーズとは限らず、束帯の図で陥りがちなポイントです。 |
|
| 逢ひ見ての 後の心に くらぶれば 昔は物を 思はざりけり 「拾遺集」 | |
 |
大中臣能宣朝臣 (921〜991) |
| 神祇小祐・大祐・小副・大副をへて伊勢神宮祭主、正四位下 | |
| 衣冠姿です。 細かく描く絵師にしては黒袍に文様が無いことが意外です。指貫は紫で八藤丸の文様。四位の衣冠としての指貫は通常は紫無紋ですが、禁色を許された場合は有紋の指貫を着用することが出来ました。ここでは彼が禁色勅許を得たということにしておきましょう。手にしているのは笏で、神拝のとき以外には衣冠には用いられませんが、神官である彼のこと、これも特別扱いです。 |
|
| 御垣守 衛士のたく火の 夜は燃え 昼は消えつつ 物をこそ思へ 「詞花集」 | |
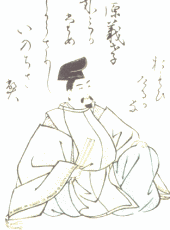 |
藤原義孝 (954〜974) 疱瘡のため20歳で早世 |
| 侍従・左兵衛佐をへて右少将、正五位下 | |
| 無紋の生成り色の狩衣、単は白で指貫は浅黄色。風折烏帽子です。 どう考えてもこれは義孝には似合いません。だいいち、20歳でなくなった彼をこう老け顔にしては・・・。装束の色味から考えると、これは地下人の布衣のように見えます。 有職故実について知識がある絵師としては、何か考えるところがあったのでしょうか・・・? |
|
| 君がため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな 「後拾遺集」 | |
 |
藤原実方朝臣 ( 〜998) |
| 左近少将・右馬頭などをへて従四位上右左近中将のち陸奥守へ左遷 | |
| これは珍しい、舞楽装束です。巻纓に老懸、「挿花」をさした冠、青刷り文様のある「東遊」の袍、表袴も刺繍入りのカラフルなものです。 実方は清水臨時祭の舞人を務めたことも有名なので、そのときの姿を描いたのでしょう。絵師の有職故実と古典文学への造詣の深さが見て取れます。 実方は光源氏のモデルの一人とも言われるほど恋の逸話に彩られた人物で、どう描くか悩んだことでしょう。しかし髭はどうでしょうか・・・。 |
|
| かくとだに えやはいぶきのさしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを 「後拾遺集」 | |
 |
藤原道信朝臣 (972〜994) 関白道兼の養子 23歳で早世 |
| 左近中将・美濃権守、従四位下 | |
| 藤立涌と思われる立涌文様の狩衣、浅黄色の指貫、風折烏帽子です。 藤原義孝と同様、早世した彼を描くには老け顔です。このシリーズではほとんどの男子が八の字髭、顎髭をたくわえています。また風折烏帽子がまるで直垂の引立烏帽子のように見えることも残念です。この絵師は武将絵が得意だったのでしょう。戦国大名の図のようにさえ見えます。 太刀が飾太刀なのは狩衣姿にはそぐいません。太刀を描くならば毛抜き形の野太刀にすべきです。狩衣の袖の肩が折り返っていますが、これは他にも例が見られます。何を表しているのでしょうか・・・。 |
|
| 明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき 朝ぼらけかな 「後拾遺集」 | |
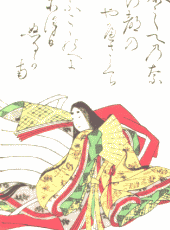 |
伊勢大輔 生没年不詳 大中臣輔親の娘、高階成順の妻 |
| 中宮彰子に出仕 | |
| 唐衣・裳をつけた女房装束、いわゆる十二単の正装です。 萌黄色の単ですが、裏返った部分は黄色で描かれ、これは色指定ミスではなくて「裏」を表す技法の一種でしょう。 彼女の身分からすると、いささか豪華すぎる装束のような気もしますが・・・。 |
|
| いにしへの 奈良の都の八重桜 けふ九重に にほひぬるかな 「詞花集」 | |
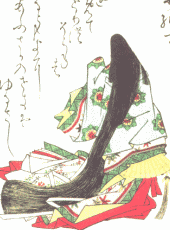 |
清少納言 (965〜?) 清原元輔の娘 |
| 中宮定子に出仕 | |
| これもわかりにくいですが十二単の正装です。 伊勢大輔と同じく萌黄の単の裏を黄色で表していますが、どうしたことか文様がありません。これは重大なミスですねぇ。単の文様は三重襷。伊勢大輔は幸菱を描いていますが、この描き分けは何か理由があったのでしょうか・・・。 |
|
| 夜をこめて 鳥の空音は はかるとも よに逢阪の 関はゆるさじ 「後拾遺集」 | |
 |
左京大夫道雅 =藤原道雅 (992〜1054) |
| 中務権大輔・美作守等を歴任し、正三位左京大夫 | |
| 左京大夫にしてはチープな狩衣姿です。引立烏帽子のような風折烏帽子ということもあり、これもまたまるで武家のように見えます。 狩衣は香色で飛蝶の文様、指貫は浅葱色無紋です。このシリーズでは直衣の指貫は紫有紋、狩衣の指貫は浅葱または萌黄無紋と決めているようですね。それはそれで身分を考えれば妥当とも言えますが、道雅には相応しいものではないでしょう。 太刀は円形の「しとぎ鍔」をつけた野太刀で、狩衣には適格です。 |
|
| 今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを 人づてならで いふよしもがな 「後拾遺集」 | |
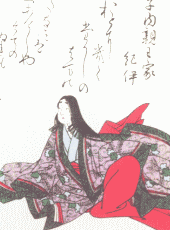 |
祐子内親王家紀伊 生没年不詳 紀伊守藤原重経の妻、または妹 |
| 後朱雀天皇皇女高倉一宮祐子内親王家に出仕 | |
| 袿袴の姿です。 身分からすれば妥当な装束です。袿の文様は桐唐草を描いています。小袖が浅黄色なのはデザイン上の都合と考えられます。 興味深いのは座り方がわかることで、見事に片立膝で座っていることを描いています。 |
|
| 恨みわび ほさぬ袖だに あるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ 「後拾遺集」 | |
 |
源俊頼朝臣 (1055〜1129) 源経信の三男 |
| 右近衛少将・左京権大夫をへて、従四位上木工頭 | |
| なんとも風流な狩衣での立ち姿です。 萌黄の菊立涌文様の狩衣、紅の単に浅葱色の指貫、浅沓です。手に持つのは「中啓」でしょう。 風になびく姿が秀逸です。現代の狩衣は糊がしっかりとした「こわ装束」ですが、平安の「なえ装束」の狩衣は、このような感じだったのでしょうか。ただ、この場合絵師はそこまで考えていたとは思えず、江戸浮世絵風の描き方と見るべきでしょう。 |
|
| 憂かりける 人を初瀬の 山おろしよ はげしかれとは 祈らぬものを 「千載集」 | |
 |
藤原基俊 (1060〜1142) |
| 官途には恵まれず、従五位上左衛門佐で退官 | |
| 香色に若松唐草を散らした文様の狩衣、紅の単に浅黄色の指貫です。 狩衣の裏が白いですが、裏白の狩衣は40歳(当時の老人)以降に見られるならわしです。80代まで生きた彼を描いているとも言えましょう。 烏帽子は風折烏帽子。形からいかにも風折りですが、そうすると上で見てきた烏帽子は「引き立て」なのでしょうか?狩衣にはあり得ない組み合わせなのですが・・・。 |
|
| 契りおきし させもが露を 命にて あはれ今年の 秋もいぬめり 「千載集」 | |
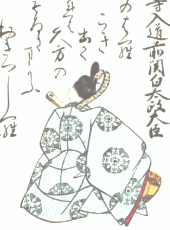 |
法性寺入道前関白太政大臣 = 藤原忠通 (1097〜1164) |
| 内大臣・左大臣・太政大臣を歴任 関白 | |
| 冬の冠直衣です。 珍しいのは指貫が朽葉色の八藤丸文様であること。あり得ないものではありませんが、このシリーズでは異質です。また直衣の袍が「四白」になっていません。檜扇を持つなど線画段階での構図は間違いのないものですから、これは色指定の誤りか刷師のミスかもしれません。 |
|
| わたの原 漕ぎ出でて見れば ひさかたの 雲居にまがふ 沖つ白波 「詞花集」 | |
 |
後徳大寺左大臣 = 藤原実定 (1139〜1191) |
| 大納言・左大将・内大臣・右大臣をへて左大臣 | |
| 冬の烏帽子直衣です。 こちらは指貫も紫、袍も「四白」でもっとも典型的で正確な図で、まるで摂関御影図を見ているようなすっきりとした構図です。 |
|
| ほととぎす 鳴きつる方を ながむれば ただ有明の 月ぞ残れる 「千載集」 | |
 |
藤原清輔朝臣 (1104〜1177) 六條家 |
| 太皇太后宮大進から二條天皇の歌合判者等をへて最終的に正四位下 | |
| 薄紫色の水流と飛鳥の文様の狩衣、単は浅縹、指貫は薄萌黄です。 この風折烏帽子も風折りらしい図柄です。上で見てきた引立烏帽子のような烏帽子はどうも狩衣に似合わず、恵比須像などを意識したものかもしれませんね。 室町以降、風折烏帽子は上皇か地下人が用いるもので、五位以降の「堂上」は用いませんでした。その意味でも文様のある狩衣には相応しくありません。 |
|
| 長らへば またこのごろや しのばれむ 憂しと見し世ぞ 今は恋しき 「新古今集」 | |
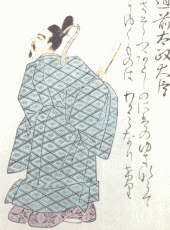 |
入道前太政大臣 =藤原公経 (1171〜1244) 西園寺家の祖 |
| 鎌倉幕府と親密で、承久の乱後に太政大臣 | |
| 夏の冠直衣です。珍しい後ろ姿です。 袍は縹色三重襷文様。指貫は鳥襷です。問題点としては背中に「はこえ(格袋)」が見えないことで、直衣ならば「はこえ」は表に見えるはずです。また襴の「蟻先」が変な位置に見えますが、これは描き方が不足です。絵師は絵巻物を参考にして描いて、実物を見たことがなかったのかもしれませんですね。 |
|
| 花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり 「新勅撰集」 |